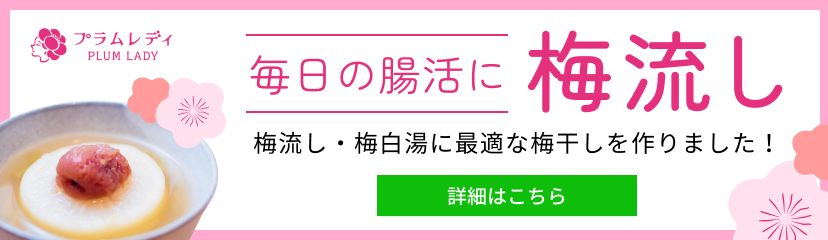市販の梅干しは干さなくても食べられますが、自分で梅干しを作る場合は梅を干すなど作業が必要です。
梅は干すことで保存性を高められ、味も良くなるので、自分で干し方を身につければいつでも美味しい梅干しを食べられるようになります。
本記事では、梅を干すメリットや梅の干し方、注意点などを徹底解説します。
梅干しの作り方や干し方を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
梅を干すことによる2つのメリット
梅を干すことにはさまざまなメリットがあります。
本章では以下の2つのメリットについて解説するので、参考にしてください。
- 保存性が高まり長い間食べられるようになる
- ねっとりとした食感になり風味が芳醇になる
それぞれ詳しく解説します。
保存性が高まり長い間食べられるようになる
梅は干すことで保存性が高まるため、長い期間食べられるようになります。
保存性が高まる理由は、乾燥によって水分が減り、腐敗の原因となる菌が繁殖しにくくなるからです。
また、梅を天日干しにして太陽光に当てるとクエン酸が凝縮されて、腐敗の原因となる菌を死滅させる効果も期待できます。長期間保存しておきたい場合、「直射日光に当てること」が梅の干し方で重要なポイントです。
一方、梅を干さないで作る梅漬けは、干した梅よりも保存期間が短くなります。
梅干しの賞味期限については、以下の記事を参考にしてください。
参考:【種類別】梅干しの賞味期限は?賞味期限切れでも大丈夫?保存方法も解説
ねっとりとした食感になり風味が芳醇になる
梅を干すと味や食感にも良い影響があります。
梅の水分量は干すことで一気に減ります。水分が減ることで梅の酸味が飛び、旨味が増して美味しくなるのです。
梅を干すひと手間を加えるだけで、酸味や旨味が凝縮され、より濃厚な風味になります。
反対に、梅を干さなければとがった塩気や酸味が強く、人によっては食べにくいと感じます。
また、梅の水分が抜けることで、果肉がねっとりとした食感になります。
梅表面の塩が再結晶化し、浸透圧により梅果汁が出て梅干しの食感が変わるのです。
美味しい梅干しを作るためにも、梅の上手な干し方をぜひマスターしてください。
一般的な梅の干し方を紹介
本章では、一般的な梅の干し方について解説します。
ポイントは、晴れた日に3日間続けることです。
以下で3日間の行程を詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
梅の干し方1日目の工程
梅の干し方1日目の工程を順に解説します。
梅の状態:梅干しを作る前の段階で洗って水気を拭き取った状態。
作業手順:
1. 晴れた日を選び、天日干しするスペースを用意します。風通しの良い場所が理想です。
2. 梅を広げ、直射日光の当たらない場所に並べます。梅同士が密着しないように間隔をあけて配置します。
3. 午後からは直射日光の当たる場所に移して、さらに乾かすのがおすすめです。
4. 夕方になったら、梅をひっくり返してもう一度拭きます。
5. 梅を取り込み、きれいな容器に詰めて冷暗所で保管します。
梅を天日干しにする際は、一つひとつを丁寧に拭いてほこりやカビがないことを確認することが重要です。
梅を庭やベランダに干す時は、通気性を確保するため、ざるを地面に直接置くのは避けてください。
ざるの下に小さめの煉瓦やコンクリートブロックを並べると良いです。
容器に残った梅酢も一緒に天日干しすると、殺菌効果で保存性が高まります。
梅の干し方2日目の工程
梅の干し方2日目の工程を順に解説します。
梅の状態:1日目の天日干しを経て、梅の表面が固くなっている状態。
作業手順:
1. 梅を広げ、直射日光の当たる場所に並べます。梅同士が密着しないように間隔をあけて配置します。
2. 1日目と同様に梅を太陽の光と風に当てながら、1日干し上げます。梅の水分がより一層蒸発して、梅がさらにしっかりと固くなることを目指します。
3. 昼過ぎになったら、梅をひっくり返してもう一度拭きます。
4. 夕方になったら、梅を取り込み、きれいな容器に詰めて冷暗所で保管します。
2日目を経て、1日目よりも梅の表面が固くなり、しわが増えていれば順調です。
梅の干し方3日目の工程
梅の干し方3日目の工程を順に解説します。
梅の状態:2日目の天日干しを経て、梅の水分がさらに減って固くなっている状態。
作業手順:
1. 梅を広げ、直射日光の当たる場所に並べます。梅同士が密着しないように間隔をあけて配置します。
2. 1日目と2日目と同様に梅を太陽の光と風に当てながら、1日干し上げます。梅の水分がさらに少なくなり、表面が完全に固くなるまで干します。
3. 昼過ぎになったら、梅をひっくり返してもう一度拭きます。
4. 夕方になったら、梅を取り込み、きれいな容器に詰めて冷暗所で保管します。
天日干しの間、晴れた日であれば毎日同様の作業を行い、梅の水分をしっかりと飛ばすことが重要です。
梅の表面が完全に固くなり、触るとカサカサとした感触になるまで干してください。
干した梅干しの保存法については、煮沸消毒した容器に入れて密封し、冷蔵庫で保存するのが良いです。
梅を干すポイント
梅を干すにあたって、いくつかのポイントがあります。
具体的には以下の3つに注意して梅を干すのが重要です。
- 土用ざるや干カゴを用意する
- 3日間晴天が続く日を選んで梅を干す
以下で詳しく解説していきます。
①土用ざるや干カゴを用意する
土用ざるや干しカゴを用意することで、梅干し作りの品質向上、衛生管理、日光利用、作業効率の向上に繋がります。
具体的には以下の効果があります。
・均一な乾燥:土用ざるや干しカゴを使用すると、梅が均一に風通しの良い状態で干すことができます。これにより、梅の全ての部分が均等に乾燥し、品質を均一に保つことができます。
・衛生面:土用ざるや干しカゴを使用することで、梅が地面に触れることを避け、汚染や虫害のリスクを減少させます。土や雑菌が梅に付着することを防ぎ、食品の安全性を確保します。
・日光の利用:土用ざるや干しカゴを使用すると、梅を直射日光に当てて効果的に乾燥させることができます。これにより、紫外線による殺菌や風による通気効果を最大限に引き出すことができ、梅の品質向上に繋がります。
・作業の効率性:土用ざるや干しカゴを使えば、梅の管理や取り扱いがしやすく、生産効率が向上します。梅がきちんと並んでいるため、干す・取り入れる作業がスムーズに進み、手間を減らせます。
②3日間晴天が続く日を選んで梅を干す
梅を干す際は3日間連続で晴れが続く日を選ぶのがおすすめです。
3日間連続の晴れを選ぶことで、梅干しの品質を向上させ、長期保存の安全性を確保し、効果的な干し方を実現できるからです。
具体的には以下3つの理由があります。
・梅の乾燥品質向上:晴れた日は湿度が低く、風通しが良いため、梅が均一に乾燥しやすくなります。湿度が高い日や雨の日に梅を干すと、湿気が含まれたままで、品質が低下しやすくなります。
・防腐効果:梅を晴れた日に干すことで、自然の殺菌効果が得られます。紫外線や風によって、細菌やカビの発生を抑制し、梅干しを長期間保存する際の安全性を高めます。
・早い乾燥:3日間連続の晴れは、梅の水分を早く蒸発させるのに適しています。これにより、梅干し作りが効率的に進み、梅が長時間外部の要因にさらされないようにすることができます。
梅の干し方に注意!やってはいけないNG行為5つ
梅の干し方は簡単ですが、方法を一つ間違えると、失敗してしまう可能性があります。
ここでは、梅の干し方で注意したい、やってはいけないNG行為を5つご紹介します。
- 金属製のザルや器具・ネットなどを使う
- 極端に温度が高くなる場所で干し工程を行う
- 梅干し同士の間隔を空けずに干す
- 湿度の高い日や雨の日に梅干しを干す
- 室内の日が当たらない場所で梅干しを干す
以下で詳しく解説します。自分で梅を干す際は十分に気をつけてください。
①金属製のザルや器具・ネットなどを使う
梅を干す際には、金属製のザルや器具は使わないようにしてください。
なぜなら、梅は酸性の食材であるため、金属が錆びたり溶けてしまったりする可能性があるからです。
また、金属やステンレスなどは熱で膨張しやすい素材であり、天日干しの際に高温になることもあります。
溶けた金属の影響で、梅干しの味が悪くなってしまう恐れもあるため、注意が必要です。
以上の理由から、使用する道具やザルには竹製のものを選ぶのがおすすめです。
市販の梅干し専用のざるやネットなどを活用するなど工夫してください。
②極端に温度が高くなる場所で干す
梅を干す場合は、日陰ではなく直射日光に当てるのが望ましいです。しかし、極端に温度が高いところで梅を干すと、品質が悪化してしまうことがあります。
特にコンクリートやアスファルトの上や車の上などには、梅干しのざるを置かないようにしてください。
また、熱が伝ってこない場所でも、あまりに温度が高すぎる場所は危険なので避けるべきです。
ベランダなど限られた空間にしか干せない場合は、なるべく温度の低い場所を選んでください。
真夏の日中など温度が高くなりすぎる場合には、日当たりが良い室内などに場所を移すと良いです。
このように、極端に温度が高くなる場所で梅を干すのはおすすめしません。
③梅同士の間隔を空けずに干す
隣り合った梅の間隔を空けずに干すと、梅同士がくっついてしまい、上手く乾燥しない可能性があります。
また、梅がくっついた状態だと、部分的に水分が残りやすくなり、カビの発生を促進する原因にもなりかねません。
梅を干す際には、梅と梅の間隔を1㎝以上空けるようにしてください。
梅を干す際には、できるだけ多くの梅を広げて干せるよう、広い場所を確保するのがおすすめです。
④湿度の高い日や雨の日に梅を干す
湿度の高い日や雨の日に梅を干すと、梅が腐りやすくなるため注意が必要です。
湿気や水分を含むと梅の乾燥が進まなくなるため、風味や香りなども落ちがちです。
また、雨で梅が濡れてしまうとカビが発生する恐れもあります。
梅を干す日数は最低でも3日間必要なので、梅雨や秋の長雨時期は必ず避けるようにしてください。
もし、梅を干している最中に雨が降ってきた場合、すぐに取り込み、濡れた梅干しをキッチンペーパーなどで拭き取ります。
全体的に濡れた時は、ホワイトリカーや焼酎などで消毒するとカビが生えるのを防げます。
⑤室内の日が当たらない場所で梅を干す
室内で梅を乾燥させること自体は問題ありません。しかし、日が当たらない部屋で梅を干すと、天日干しに比べて乾燥が遅くなる可能性が高いです。
室内で乾燥させる場合は、日当たりが良い部屋を選ぶのがベストです。
ただし、梅を乾かすのにエアコンを使うのはおすすめできません。
なぜなら、エアコンの風には埃やカビが混ざっていることがあり、梅に付着するとカビの原因になるからです。
梅を干す際は自然乾燥が望ましいですが、どうしても室内干しをする場合は乾燥剤を使うのがおすすめです。
ざるや水切かごに梅を並べて、その横に乾燥剤を置くことで効率的に乾燥を進められます。
梅の干し方に関するよくある質問
初めて梅を干す方はさまざまな疑問を抱くと思います。しかし、梅は干し方のコツさえ知っておけば、誰でも簡単に干すことが可能です。
ここでは、梅の干し方でよくある質問とその回答をまとめていきます。
- 梅干しを乾燥させるのにぴったりの時期はいつ?
- どのくらい梅をつけてから干すようにするのが良いの?
- 干している途中で天気が悪くなったらどうしたらよい?
- 梅干しをベランダで干すやり方は?
- 梅干し専用のザルが手に入らないとき干し方はどうする?
- 梅干しを干さない作り方もあるって本当?
以下で詳しくお答えします。
梅を乾燥させるのにぴったりの時期はいつ?
梅干しを上手に作れるのは7月中旬から8月上旬頃です。
この時期に梅を干す「土用干し」は古い慣習でも知られています。
梅干しにぴったりの完熟梅を収穫し、梅干しにするのが6月の半ばから7月にかけてです。
その梅干しが出来上がってくる時期が梅雨明けごろのため、干すのにはちょうど良い時期となります。
雨天が続くと梅が干せないため、梅雨シーズンである6月に梅を干すのはおすすめしません。
近年は暑い時期が以前に比べて長いため、梅を9月に干すケースも増えています。
どのくらい梅をつけてから干すようにするのが良いの?
出来上がりをよくするには、一ヶ月ほど漬け込んだ梅を干すのがおすすめです。
漬ける時期が一ヶ月以下になると、梅の味や柔らかくなりません。
一ヶ月ほどしっかり漬け込んだ梅を適切な工程で干すようにしてください。
また、梅を干すまでは、密封された容器で常温や冷蔵庫で保存しておきます。
塩分濃度が15%以下の梅は冷蔵庫で保存するのをおすすめします。
干している途中で天気が悪くなったらどうしたらよい?
雨が降らないうちは、基本的にそのまま干していても問題ありません。しかし、雨が降り出した際には、梅を室内に取り込むようにしてください。
室内に取り込んだ梅は、扇風機などの風を当てて乾燥させます。
ただし、梅の干し方は、晴れた日に天日干しするのがベストです。天気が回復したら、あらためて天日干しするようにしてください。
梅をベランダで干すやり方は?
マンションやアパートなどに住んでいて梅を干すスペースが少なくても、干すことが可能です。
大きなざるを置けない場合は、洗濯用の平干しネットやひもの干し用のネットで代用するのがおすすめです。
物干し竿にかけるだけで良いので簡単に用意でき、雨が降ってもすぐに取り込めます。
これらのネットを使う場合は、ネットの底に巻きすを敷き、その上に梅を並べます。
通常の天日干しと同じように、梅を干す時はくっつかないように間隔を空けてください。
また、梅酢が垂れてくる可能性があるため、ネットの下に新聞紙などを敷いておくと良いです。
梅専用のザルが手に入らないとき干し方はどうする?
梅の干し方でよく質問にあがるのが「専用のざるがないときはどうすればいいのか」というものです。
平干しネットやひもの干し用のネット、食器用水切りかごのほかに、野菜干し用の吊り下げネットでも代用できます。
ただし、梅専用のものと違って日当たりにムラがでやすい点には注意が必要です。
また、お盆に網などを載せた上にキッチンペーパーを敷いて干す方法もあります。
キッチンペーパーで干す際には、梅がキッチンペーパーにくっつかないように、こまめに裏返してください。
梅を干さない作り方もあるって本当?
梅を干さないで作る梅漬けというものもあります。
通常の梅干しの作り方のように天日干しを行わず、梅を塩漬けしただけのものです。
塩気や酸味が染み込んでいるため、しょっぱい味の梅干しになります。
梅本来の味が楽しめるので、おにぎりの具材にしたりご飯に合わせたりするのに人気です。
梅漬けの簡単な作り方は次の通りです。
- 梅を水洗いする
- 梅のヘタを取って水気を拭く
- ボウルに梅と塩を入れて混ぜる
- ジップロックの内側を消毒する
- 4に3を入れて密閉する
- ジップロックを深めの容器(金属製以外のバットなど)に入れる
- 重石をのせる
この方法で作った梅漬けは、1ヶ月程度で食べられるようになります。
【まとめ】梅の干し方をマスターして風味や保存性を高めよう
今回は梅の干し方について解説しました。
梅の干し方をマスターすれば、風味や保存性に優れた梅干しを作ることが可能です。
また、梅干しをさらに乾燥させて作る「干し梅」もおやつに人気です。干し梅の作り方については、別の記事で紹介しています。
自宅で梅干しを干すのが難しい方は、梅干しをオンラインショップで購入することもご検討ください。
プラムレディでは、和歌山県の紀州産南高梅を使った梅干しを多数取り揃えております。
ご自宅で料理のお供に、誰かの贈り物に美味しい梅干しを選んでみてください。
手軽に梅干しを楽しむならプラムレディがおすすめ
「おいしい梅がなかなか手に入らない」「美味しい梅干しを手軽に食べたい」と考える方には、「プラムレディ」がおすすめです。
定期的にキャンペーンセールを実施しており、より手軽に梅干しが楽しめるのも嬉しいポイントです。
ここでは、プラムレディがおすすめな理由を3つご紹介いたします。
理由➀高品質な梅干しがセール価格で楽しめる
プラムレディで取り扱うのは、厳選された梅商品です。キャンペーン期間中は、以下の商品がとくにおすすめです。
ご家庭で楽しめる梅干しから、木箱に入った個包装の高級梅干しも。はちみつのやさしい甘さや昔ながらの塩味が楽しめるものまで、幅広いラインナップです。
理由➁ポイントが貯まる
プラムレディでは、会員登録後、ログインしてご購入されると金額に応じてポイントが付与されます。貯めたポイントは、1ポイント=1円として次回以降のご注文時にご購入代金の一部としてご利用いただけます。
※お電話やFAXでのご注文の場合、ポイントは付与されません。
いつもよりお得に商品を購入いただくことができます。
理由➂全国どこでも配達可能
プラムレディでは、日本全国に梅商品を配達することができます。
遠く離れた方へ感謝の気持ちや長寿の願いを込めて、一粒ひとつぶが厳選された梅干しをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。