梅干しの塩分取りすぎは危険?梅干しの塩分量について解説
梅干しは、強い塩味が特徴的な食品で、塩漬け梅と調味漬け梅では塩分濃度が異なります。主にカビの発生を防止するなどの理由から、梅干しの塩分濃度は濃いと考えられていますが、塩分摂取量の過多は高血圧につながるため注意が必要です。
今回は、梅干しの塩分についてご紹介します。梅干しに含まれる塩分量や塩分を控える方法などについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください!
また、塩分控えめな梅干しのご紹介もしています。人気の高い高品質な梅干しを購入したい方は、必見です!
Contents
梅干しの塩分の平均はどれくらい?
梅干しの可食部100gに含まれる塩分量は、以下の表のとおりです。
| 梅の種類 | 塩漬け(※1) | 調味漬け(※2) |
| 塩分量(100gあたり) | 18.2g | 7.6g |
表を見ると、調味漬けに比べて昔ながらの塩漬け梅干しは、塩分含有量が2倍ほど多いことが分かります。
梅干し1粒あたりの重量は約20gで、廃棄率は25%のため全体の約3/4gは可食部と計算できます。そのため、梅干し1つあたりの可食部は約15gです。
上記の計算から、梅干し1粒に含まれる塩分量は、塩漬け梅干しで約2.7g、調味漬け梅干しで約1.1gになります。
参考
1:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 果実類/うめ/梅干し/塩漬
2:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 果実類/うめ/梅干し/調味漬
梅干しの塩分が濃い理由 
梅干しはなぜ塩分を多く含ませてつくられるのでしょうか。じつは、梅干しに塩を使用するのには、きちんとした理由があります。
- カビを生えにくくするため
- 長期保存するため
昔は、現代のような技術が発展しておらず、食品を腐らせないようにする方法は手探りで考えられていました。梅は塩分濃度が濃いほどカビが生えにくいとされ、伝統的な製法で代々つくられ、いまに至ります。
また、塩分濃度の高い梅干しはカビが生えにくいだけでなく長期保存にも向いているため、昔は塩分濃度の濃い梅干しが主流でした。近年では、健康志向の方が増えたことによって塩分濃度の低いさまざまな調味漬け梅干しが普及していますが、昔ながらの塩漬け梅干しも根強い人気があります。
梅干しの塩分の取りすぎは危険?
食への健康志向が高まった中で、梅干しに含まれる塩分に注目が集まっています。塩分の摂りすぎは以下のような症状につながる恐れがあるため注意が必要です。
- からだが浮腫む
- 血圧が上昇する
からだが浮腫む
塩分を大量に摂取すると、喉が乾きます。これは、塩分を摂ったことで血中のナトリウム濃度が高くなり、からだが正常に戻そうと水分を欲するためです。
だからといって水分をたくさん飲みすぎると、今度は体内の水分量が多くなります。結果、からだのむくみにつながります。
血圧が上昇する
塩分の摂りすぎは、むくみだけでなく血圧の上昇にもつながるため注意が必要です。
頻繁に血圧の上昇が起こると、血管壁にかかる圧力が次第に強くなります。高血圧症と診断された場合は、日常的に塩分制限の生活をしなくてはなりません。
ちなみに日本では3人に1人が高血圧と言われています。主に塩分の摂りすぎが原因であるため、高血圧は食事との関わりが強いことが分かります。
高血圧の症状が見られる方は、とくに塩分の摂取には気をつけましょう。
塩分摂取量は1日どれくらい? 
日本人の1日の塩分摂取量の目標量は、男性で7.5g未満、女性で6.5g未満とされています。(※3)しかし、国の調査結果によると、日本人の1日の食塩摂取量の平均は、男性で11g、女性で9.3gと、目標量を大きく上回っているのが現状です。(※4)
これは、家庭料理や外食など日常的な塩分摂取量が多いことを示しています。塩分摂取量を目標量に近づけるためには、日々の食事で摂る塩分への意識が欠かせません。
とくに、高血圧を発症している方は、塩分摂取量を6g未満に抑える必要があるため、健常者に比べてより塩分制限が必要です。
しかし、ミネラルを失いがちな夏の日などは、塩分を補給してバランスをとることも大切です。「どれくらい食べるか」「どうやって食べるか」自分で選択をしながら栄養を補給することが大切なポイントといえるでしょう。
参考:
3:厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年)
4:厚生労働省『平成 30 年国民健康・栄養調査結果の概要』
梅干しの塩分を控える方法
程よい塩味と酸味が楽しめる梅干しは、朝ごはんのお供として活用する方も多いのではないでしょうか。梅干しを楽しむ方のなかには、「梅干しを食べたいけど塩分量が気になる」といった方もいるでしょう。
そこで、梅干しの塩分を控える方法をご紹介します。主な方法は、以下の3つです。
- 塩分濃度の低い梅干しを選ぶ
- 梅干しのサイズを変える
- 塩抜きをする
それぞれのポイントを詳しく解説します。
塩分濃度の低い梅干しを選ぶ
梅干しは、商品によってそれぞれ塩分量が異なります。
たとえば、先ほどの表のとおり、調味漬け梅干しは塩漬け梅干しよりも塩分量が低い傾向にあります。塩分が気になるけど梅干しが食べたいという方には、塩分控えめで甘みが楽しめるはちみつ梅干しなどの調味漬け商品がおすすめです。
また、お店によっては塩分を抑えた減塩梅干しなどもあります。パッケージの塩分量を確認し、なるべく塩分が控えめな梅干しを選びましょう。
梅干しのサイズを変える
梅干しの塩分が気になる方は、粒のサイズで梅干しを選ぶのもおすすめです。
小粒の梅干しを選べば、塩分摂取量も大粒に比べて少なくなります。また、肉厚で美味しい大粒を好む方は、梅干しを半分にして朝と夜で楽しむなど、1回に食べる量を調整する方法もあります。
梅干しを日常的に食べたいけど塩分を控えたいと考える方は、小粒の商品を選んだり1回に食べる量を調整して塩分を控える方法がおすすめです。
塩抜きをする
昔ながらの塩漬け製法でつくられた梅干しは強い塩味が特徴です。梅干し好きの方のなかには、梅干しは塩漬けしか選ばないという方も多いのではないでしょうか。
じつは、梅干しは水につけると簡単に塩抜きができます。主な手順は、以下のとおりです。
- 水を容器に入れ、塩をひとつまみ加える
- 梅干しを1に漬ける
- 冷蔵庫で30分以上保存する
- 食べる際に取り出す
梅干しは傷みが進まないよう、常温放置ではなく冷蔵庫に入れて水抜きをしましょう。水抜き時間が長いほど塩分をしっかりと抜くことができますが、長時間の漬けすぎは梅の風味の劣化につながります。
また、塩抜きした梅干しは、塩抜きをしない梅干しに比べて保存性が低下します。食べ切れる分だけ水に漬け、水抜きをしたあとは早めに食べましょう。
梅の塩気を料理に活用するのも1つの手
梅の塩気は料理に活かすことができ、塩味を楽しみながら塩分摂取量を調整できます。たとえば、梅の風味を活かしたスープは、液体をすべて飲まないようにすれば、塩分摂取量を控えることができます。
魚の煮つけに梅干しを使用すれば、魚の臭みを緩和でき、さっぱりとした風味で食べやすいのが嬉しいポイント。梅干しを料理に使用する際は、醤油など塩分が含まれる調味料を少なめにし、全体の塩分量を調整しましょう。
梅干しを料理に活かす方法は、梅の風味を楽しみたいけど強い塩気や酸味が苦手という方にもおすすめです。
梅干しは「プラムレディ」がおすすめ!塩分控えめな人気商品3選 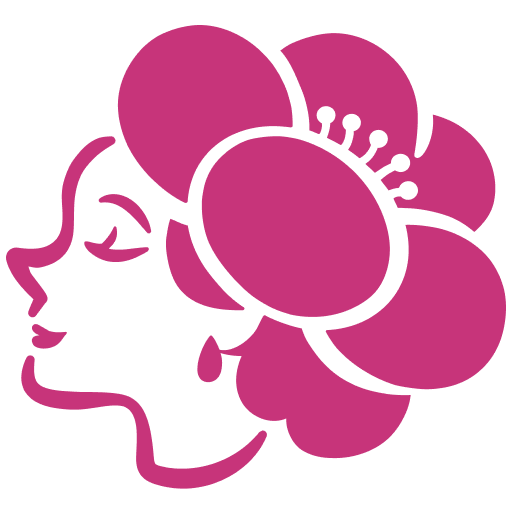
ここでは、塩分控えめの美味しい梅干しを3つご紹介します。
はちみつ梅 400~500g
和歌山県で育てられた果肉たっぷりの南高梅に、世界中から選び抜かれたフランスのはちみつを使用しています。
塩分量は100gあたり7gと控えめなため、梅干し特有の強い塩味が気になる方や小さなお子さまでも食べやすい商品です。中粒~大粒の梅干しは、食べごたえもばっちりです。
商品の詳細は、こちらをご覧ください!
紀州の梅 塩分7% 400g
大粒の特選紀州南高梅を使用した、自慢の逸品です。
塩分濃度は7%に抑え、さっぱりと仕上げました。また塩味だけでなく甘味や酸味も控えめなため、梅本来の香りや美味しさをより楽しめる商品となっています。
商品の詳細は、こちらをご覧ください!
あまちゃづる入 みなべの梅 400~500g
和歌山で採れた極上紀州南高梅を、高麗人参に含まれる「サポニン」を持つ「あまちゃづる」とともに漬け込みました。ほかにはない、新しい美味しさを楽しめる梅干しです。
また、小粒から特大粒まで、お好みのサイズから選ぶことができるのもポイント。
ちなみに「あまちゃづる入 みなべの梅 400~500g」は、プラムレディで売り上げ1位を誇る人気商品。リピーターも多く、長年愛されるロングセラー商品です。
商品の詳細は、こちらをご覧ください!
塩分を控えた梅干しを堪能しよう!
梅干しは強い塩味が楽しめる食品として、昔から親しまれていました。塩漬け梅1粒に約2.7g、調味液漬け梅1粒には約1.1gの塩分が含まれているとされ、主にカビの発生を防止する目的があります。
強い塩味が気になる方は、塩抜きをしたり塩分が少なめの梅干しを選ぶのがおすすめです。塩分の摂りすぎは血圧が高くなるおそれがあるため、摂取量に注意しましょう。
また、梅干しの購入には「プラムレディ」がおすすめです。プラムレディでは厳選された商品のみを取り扱っているため、肉厚で風味豊かな梅が堪能できます。
甘さが特徴の「はちみつ梅 400~500g」や人気の「紀州の梅 塩分7% 400g」「あまちゃづる入 みなべの梅 400~500g」は、塩分を控えながらも梅の風味を味わうことが可能です。ぜひ、ご利用ください!




